
スマートフォンがあれば、山でも安心!
そう思っていませんか?
地図、ライト、天気、通報…登山中に欠かせない機能をひとつに詰め込んだスマホは、まさに「現代の命綱」。しかしその命綱も、電池が切れた瞬間にただの重りに変わります。
今回は、30歳台の女性が実際に体験した「スマホの電源が尽きた遭難」の実例をもとに、山での電源管理がいかに命に直結するかを掘り下げていきます。
あなたのスマホ、山の中で最後まで“生き残れる”準備はできていますか?
通信手段を失うということ
30歳台の女性単独登山。
道が分からず、
地図アプリを頼りに登り続け、
日没後はスマホのライトで
足元を照らしながらの下山。
しかし、
登山口までもう少しというところで、
バッテリー残量が3%を切り、
救助要請をかけるも…
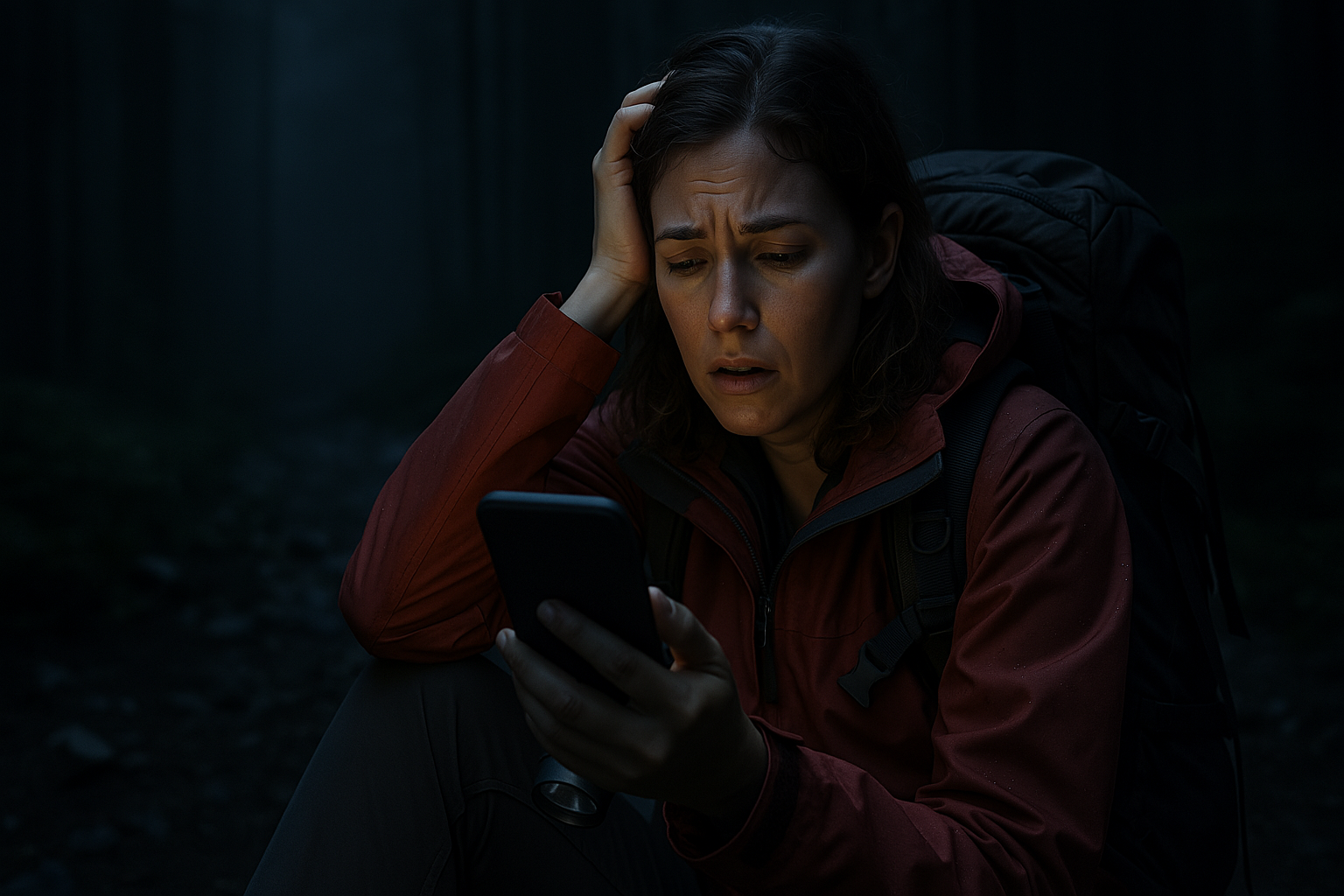
通報の途中で電源が落ち、
彼女との通信は途絶えた。
SNS投稿写真の位置情報、
GPSログ、
最終通報地点の電波情報(誤差100m)
をもとに捜索が始まったが、
本人が暗闇の中をさらに移動していたため、
特定には時間を要した。
発見時、
彼女は
「足首の骨折と左肘の開放骨折」
により動けず、寒さと孤独に耐えていた。
スマホ依存の落とし穴と、バッテリー管理の盲点
スマートフォンは
登山において「万能ツール」
に思われがちだが、
その機能は全て「電源ありき」。
山でスマホを使いすぎることにより以下のような盲点がある。
1. 電池切れによる「孤立」
• 地図、ライト、通報、位置情報すべてがスマホ頼みだと、バッテリー切れ=機能喪失
• スマホのライトで下山→大きな電力消費
• バッテリー残量が少ないと救助要請すらできないことも
2. 電波を探す動作で急速な電力消費
• 山中では電波が不安定な場所が多く、スマホが「常に電波を探している」状態に
• 特に圏外と圏内を行き来するような場所では、バッテリーの減りが極端に早くなる
3. 通信アプリやSNSのバックグラウンド動作
• Instagram、LINE、位置情報アプリなどが裏で動いていても気づかず、電力を消費
• BluetoothやWi-Fiを切っていないままだと無駄な電力ロスに
4. 地図アプリへの過信
• オフライン地図を準備していないと圏外で使えなくなる
• 画面を常時点灯しながら歩くとバッテリー消費が加速
• 登山道が非表示・ズレている地図もあり、道迷いの原因に
5. 冷えによるバッテリー性能低下
• 気温が低いとリチウムイオン電池の性能が著しく低下
• 残量があっても突然シャットダウンすることがある(特に雪山・秋の稜線)
6. 操作に気を取られ危険に気づかない
• 歩きながら地図やSNSを見て滑落・転倒する例も
• スマホを見ながらだと、周囲の音や地形の変化に気づきにくい
7. 「スマホがあるから大丈夫」という慢心
• 登山届を出さない、紙地図やコンパスを持たないなど、準備がスマホ頼みになる
• スマホが壊れた・落とした・圏外だったとき、すぐに行動不能に
モバイルバッテリー選びの注意点
- 容量不足:軽量モデル(5,000mAh)ではすぐ切れる
- 寒冷地での性能低下:気温が下がると消耗が早まる
- 電波の弱い場所:電波を探すためにバッテリーが激しく消耗
- ケーブル忘れ:端子不一致や未持参で使えないことも
信頼できる装備の条件
- 最低10,000mAh以上のモバイルバッテリー
- 防水・耐衝撃性のあるモデル
- ケーブルとセットでジップ袋に収納
- 寒い時期は内ポケットで保温

筆者のバッテリー、Anker Power Bank 10000(上)とAnker PowerCore Essential 20000(下)
日帰りでも余裕持って10,000mAh、
テント泊なら20,000mAh、
縦走なら2つ持って行きます。


コード付きなので
タイプCに揃えればコード忘れもなし、
3年ほど使っていますがトラブルなし、
2つ合わせても10,000円で購入可能。
山だけでなく日々の生活にも使えます。
節電も“命を守るスキル”
さらに電源を無駄遣いしない工夫も必要、
時にポケットの中で勝手にライト起動、
画面タッチセンサーの強弱で
雨が降ると通電して誤操作
などあるので
設定でオート機能は切っておきましょう。
- 機内モードの活用:通信を切ることで待機電力を削減
- 写真・動画撮影の制限:記録よりも命を優先
- アプリ通知の制限:バックグラウンド通信を防止
- 画面の明るさを最小に:細かい設定で消耗を減らす
まとめ:電源は“命綱”
スマホはアプリがあれば道をを示し、
電源があれば(非常用の)光を灯し、
助けを呼ぶ――
そのすべてが、「電源がある」前提です!
山で「使えないスマホ」は、
ただのオモリ、持っていないのと同じです。
スマホが、
最後まで“生きて”いるために、
バッテリーの備えを忘れないことが大事です!
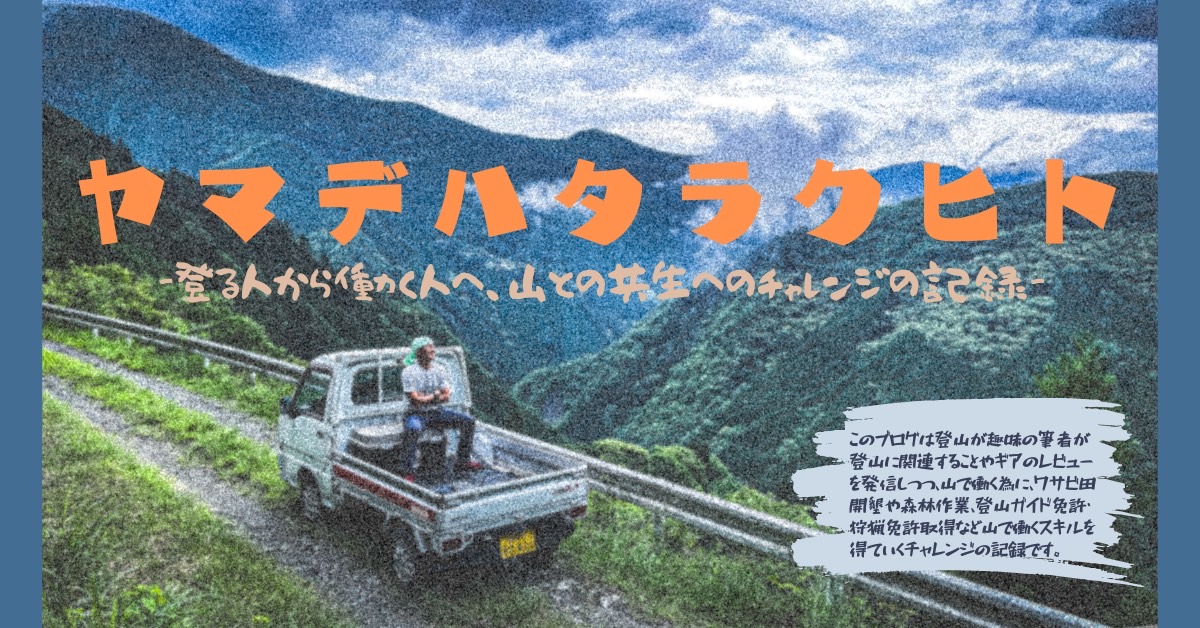
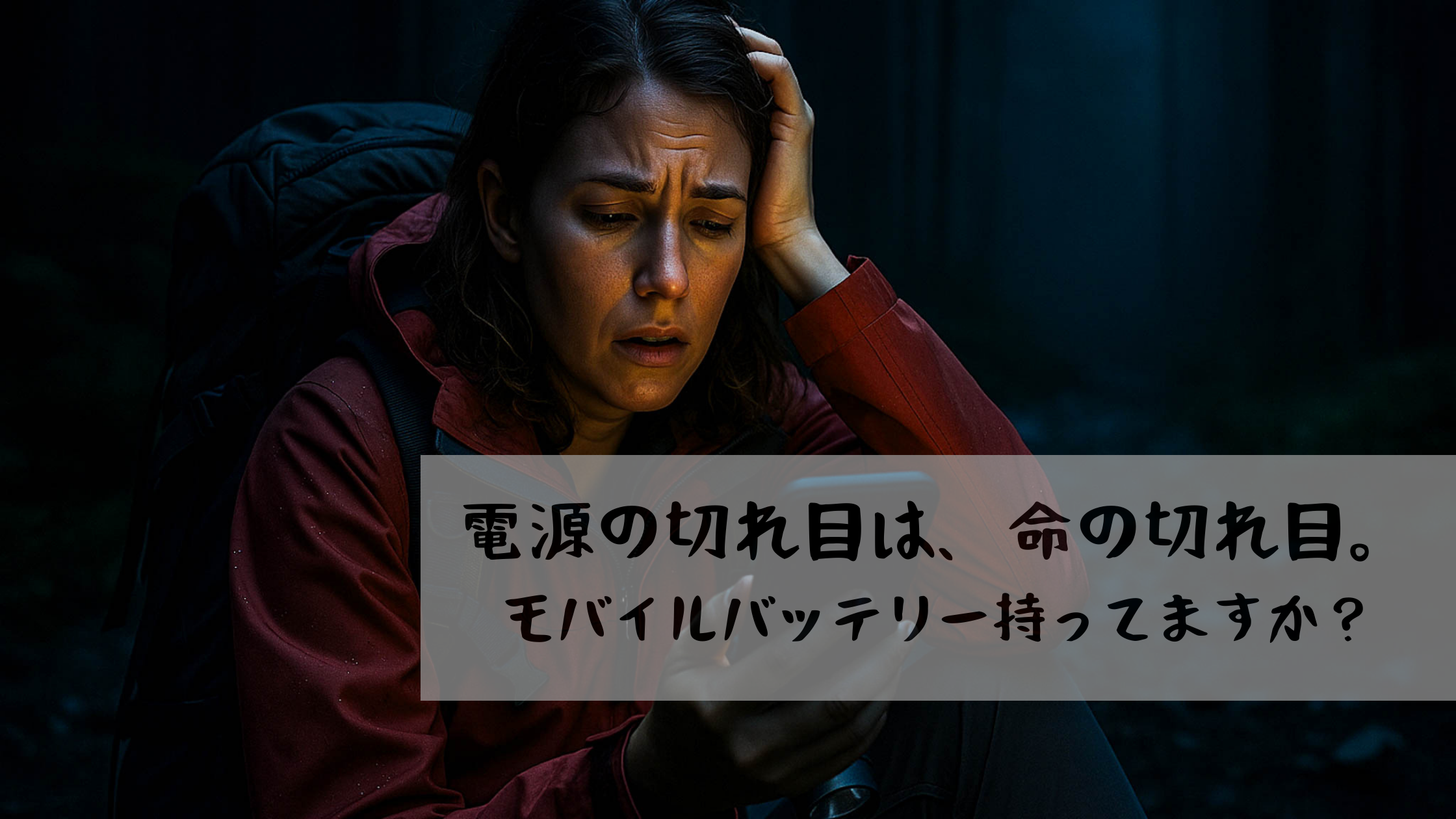
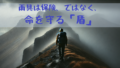

カテゴリーから探す