実例:スピードが足りず、日没前に下山できなかった話
中高年の登山者グループが、
それほど標高差の少ないコースの
計画をしていました。
登山口までは朝一番のバスで、
コースタイム的には問題ない行程でしたが、
後半になって一人の体調が急激に悪化。
思った以上にペースが落ち、
予定よりも2時間遅れで下山に。
太陽が沈み、暗くなってきたが、
ライトは点灯せず
(もっていないメンバーすらいた)。
焦って判断を誤った結果、
ルートを外れ、道迷いからの遭難要請
となりました。
これは決して特殊なケースではありません。
“歩けないほどのミス”ではなく、
“速く動けなかったこと”
が事故の引き金になった典型例です。
私が「速く動く」ことにこだわり始めた理由
私はもともとは登山者でした。
週末は奥多摩、連休には縦走。
山に行けば行くほど
「もう一つ向こうの尾根に行きたい」
「この時間でもう一座登れたら」
と思うようになり、練習にトレイルランを
取り入れるようになりました。
「最初は距離をこなすための手段」
だったはずの“走る”ことが、
いつしか、
山での判断や安全に直結する技術
であると気づくようになったのです。
「速さ」は判断力と余裕の源になる
ロングトレイルや
100kmの縦走などを繰り返す中で、
自分の行動速度と限界を
把握できるようになっていきました。
「この体調、この補給、この斜度なら、あと何時間動ける」
「今ここでやめたら、○時には下山できる」
「天候が崩れる前に、ギリギリ○○までは抜けられる」
こうした判断ができるようになったのは、
速さそのものより、自分の動きの
“幅”と“予測”を持てるようになったから
です。
山で速く動ける=安全に帰れるための“選択肢”が増える
速さは、目的地に早く着くことではありません。
速く動けるということは、
引き返す判断がしやすいということです。
予定より早く行動を終えられれば、
不測の事態への対応時間が増える
ということでもあります。
とくに次のような条件下では、
「速く動けるかどうか」
が命の分かれ道になります。
- 天候悪化が予想される時
- 日没が近い時
- 高山病や体調不良が発生した時
- 雨・雪・風で移動スピードが落ちた時
- 誰かが転倒やケガをした時
その時になって「急ごう」としても、
速く動ける体がなければ、
“急ぐこと”と“間に合うこと”は別物
だという現実に直面します。
「身体を知り、無駄を削る」ことが山の安全に直結する
ただ走るだけでは、
山での速さは持続しません。
私が身をもって学んだのは、
「身体を知り、無駄を削ることが、
安全に移動する力になる」
ということです。
「心拍が高すぎると、糖を使いすぎてエネルギーが切れる。ゆっくりだけど脂肪を燃やす“自分のペース”を掴め」
これは、ある時コーチに言われ、
強く心に残っている言葉です。
以下のような知識と体感が、リスク対応力を高めてくれました。
- AeT(有酸素性作業閾値):脂肪燃焼中心で長く動ける心拍のゾーン
- AT(無酸素性作業閾値):糖消費中心で短時間しか持たない領域
- 補給の工夫:補給ミスでスピードが落ちた時、回復にかかる時間を知っていることが命綱になる
「自分の身体がどういう状態か」
「どうすれば長く安全に動けるか」
を知っていることは、
スピードそのものよりも大切な能力
だと今は感じています。
スピードが落ちる状況こそ、リスクが増す
実際、山では次のような場面でスピードが著しく落ち、危険が増します。
- 雨で滑りやすくなった登山道
- 雪や凍結で足を取られる場面
- 夜間の視界不良
- エネルギー補給の失敗
- 高山病、脱水、下痢、吐き気など体調不良
「速く動けない状況」
=「リスクに対処する能力も低下している状況」です。
だからこそ、「走れるようにする」
ではなく、
「無理なく速く動ける状態を作っておくこと」
が何より重要なのです。
まとめ:山で速く動ける人は、判断できる人だ
私は今、「山で速く動けること」
は登山技術のひとつだと捉えています。
それは、体力任せのパワーではなく、
知識と経験と判断力の積み重ね
によって生まれるものです。
・引き返す選択肢を持つために
・余裕を生むために
・仲間を助けるために
・自分が“無事に下山する確率”を高めるために
「山で速く動けること」は、命を守る力だと、私は自信をもって言えます。
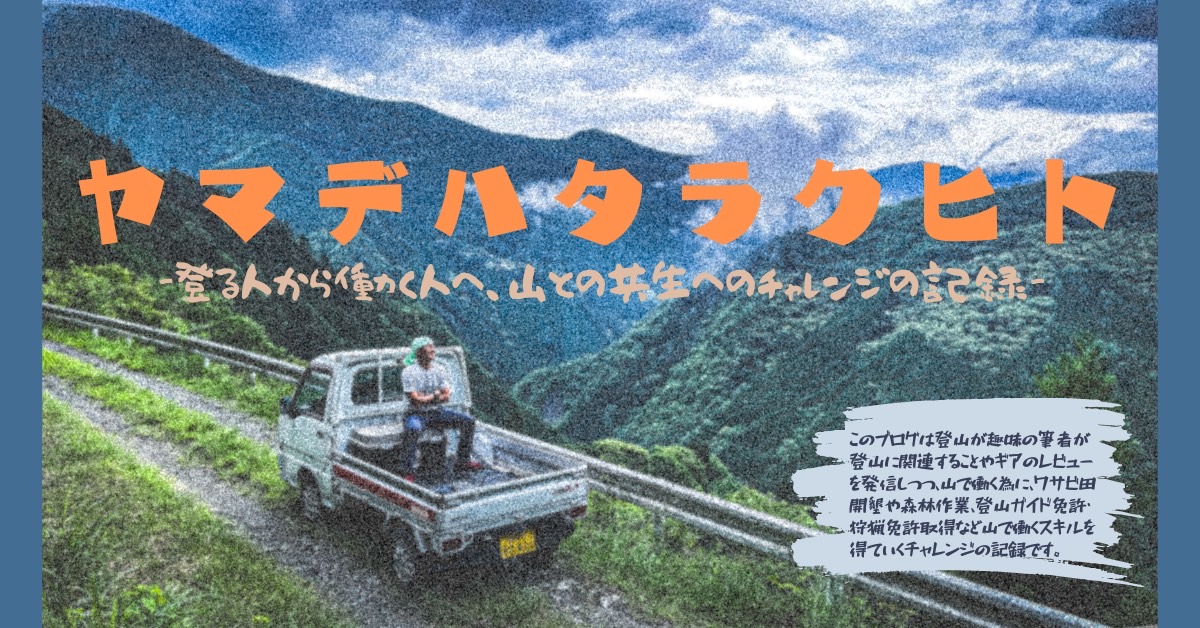
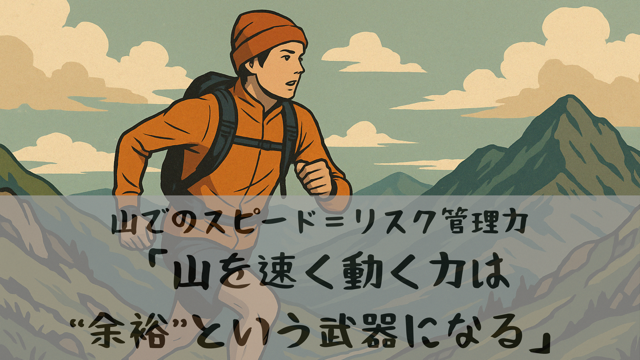
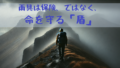

カテゴリーから探す